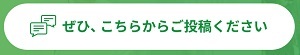50thメッセージ
50th Message- TOP
-
- 50thメッセージ
関連する団体からの祝辞(※受付順に掲載しております。)
これからも『車の両輪』として働きましょう
倉田 清子
社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を守る会 理事長
全国重症心身障害児(者)を守る会(以下守る会)が発足したのが1964年(昭和39年)であり、その約10年後にこの学会が重症心身障害研究会として発足した。功労者である小林提樹先生、糸賀一雄先生に関して多く述べられているので割愛するが、守る会が発足できたのも同先生方のご尽力によるものである。守る会の初代会長は九州大学教授であった北浦貞夫氏であり、2代目会長の雅子氏はその夫人である。雅子氏は一昨年101歳で逝去されたが、長期にわたり会長を務め守る会を発展させたカリスマ的な存在であった。守る会の歴史と本学会の歩みは同調したものであり、医療と福祉の共同作業で、雅子氏は「車の両輪」と称していた。今日の重症心身障害にあたる症状の方はもちろん古代からいたが、現在に至るまで常に未知の分野であったと思う。当初二十歳まで生きられないと医師から宣告されていたものが長命を甘受し、小児科だけでは対応するのが困難な時代になって久しい。一般の内科医などの専門医でも予測できないことが日常的に生じてきている。視点を変えてみると昭和初期、整形外科医・高木憲次博士は「肢体不自由」という名称や「療育」という言葉を提唱された。その後、びわこ学園の前身「近江学園」の設立者である糸賀一雄先生は、終戦直後から戦災孤児・生活困窮児を収容し、同時に障害児をも受け入れた。先生が残された「この子らを世の光に」という言葉は、現在でも重症児療育の指針となっている。1947年児童福祉法が制定された頃、小林提樹先生が「(日赤)両親の集い」を始められ、守る会の誕生へとつながった。当初北浦会長を中心とした母親たちが議員会館や政党本部などに「陳情」活動を行ったが、政府の回答は「社会の役に立たない者たちに税金を使うことはできない」というものであった。近年、日本の福祉はめざましい発展を遂げたが、これを後退させることなく前進させていくのが本学会、そして守る会のこれからの役割であろう。
日本重症心身障害学会 創立50周年に寄せて
加藤 光広
一般社団法人日本小児神経学会 理事長
創立50周年おめでとうございます。もっとも弱い人たちのための医学的な学術活動を半世紀の長い間続けてこられたことに心から敬意を表します。
重症心身障害は本学会(日本小児神経学会)にとっても極めて重要な位置を占めており、貴学会とは言うまでもなく密接につながっています。私自身も、国立療養所勤務の際には120名の重症心身障害の方々を受け持ち、1996年に盛岡市で開催された第22回学術集会(伊東宗行会長)に参加させていただきました。小岩井農場での懇親会は忘れがたい想い出になっています。現在も以前の勤務先で毎月診療することを楽しみにし、正月元旦の回診は年中行事になっています。
貴学会ともっとも密接に関係のある患者・家族団体は全国重症心身障害児(者)を守る会かと思いますが、3年前の理事長就任に際して、守る会の基本理念である「最も弱いものをひとりももれなく守る」を引用し、深い賛同の意を示させていただきました。50年前と比べれば医学・医療は大きく進歩し、重症心身障害を取り巻く社会状況も好転していますが、重症心身障害が最も弱い存在であることは変わりません。根底の理念は普遍的であり、専門的な職能集団としての役割や責任は益々大きくなっています。具体的には、重症心身障害と一括りにされ社会の片隅に追いやられていた集団が、遺伝学的な原因診断が可能になり、治療法開発と相まって、医学的には最先端の領域に躍り出て、古い医学的知識が役に立たないどころか進歩の恩恵を受ける機会を阻害している可能性があります。また、在宅医療の充実と受益者の増加により、重症心身障害より医療的ケア児者との呼称が社会的にはより大きく認知され、医療的ケア児支援法から漏れる重症心身障害が最も弱い存在になりかねません。こうした医学的・社会的状況を認識して情報・人的ネットワークを構築していく必要がある時代になっています。
日本の重症心身障害医療は世界一です。日本の小児神経学が最も誇るべき分野です。海外にはもっともっと弱い立場の重症心身障害の方とご家族がおおぜいいます。海外への英語論文・学術発表による情報発信と患者・医療者支援を本学会と連携して進めていただければ幸いです。
重症心身障害は本学会(日本小児神経学会)にとっても極めて重要な位置を占めており、貴学会とは言うまでもなく密接につながっています。私自身も、国立療養所勤務の際には120名の重症心身障害の方々を受け持ち、1996年に盛岡市で開催された第22回学術集会(伊東宗行会長)に参加させていただきました。小岩井農場での懇親会は忘れがたい想い出になっています。現在も以前の勤務先で毎月診療することを楽しみにし、正月元旦の回診は年中行事になっています。
貴学会ともっとも密接に関係のある患者・家族団体は全国重症心身障害児(者)を守る会かと思いますが、3年前の理事長就任に際して、守る会の基本理念である「最も弱いものをひとりももれなく守る」を引用し、深い賛同の意を示させていただきました。50年前と比べれば医学・医療は大きく進歩し、重症心身障害を取り巻く社会状況も好転していますが、重症心身障害が最も弱い存在であることは変わりません。根底の理念は普遍的であり、専門的な職能集団としての役割や責任は益々大きくなっています。具体的には、重症心身障害と一括りにされ社会の片隅に追いやられていた集団が、遺伝学的な原因診断が可能になり、治療法開発と相まって、医学的には最先端の領域に躍り出て、古い医学的知識が役に立たないどころか進歩の恩恵を受ける機会を阻害している可能性があります。また、在宅医療の充実と受益者の増加により、重症心身障害より医療的ケア児者との呼称が社会的にはより大きく認知され、医療的ケア児支援法から漏れる重症心身障害が最も弱い存在になりかねません。こうした医学的・社会的状況を認識して情報・人的ネットワークを構築していく必要がある時代になっています。
日本の重症心身障害医療は世界一です。日本の小児神経学が最も誇るべき分野です。海外にはもっともっと弱い立場の重症心身障害の方とご家族がおおぜいいます。海外への英語論文・学術発表による情報発信と患者・医療者支援を本学会と連携して進めていただければ幸いです。
50年の歩みに敬意を表します
児玉 和夫
公益社団法人 日本重症心身障害福祉協会 理事長
創立50年おめでとうございます。ここまでの貴学会の歩みに改めて敬意を表させていただきます。
小林提樹先生の「自分の経験を伝え、発展させていきたい」という願いではじまった貴学会(当初は研究会)は、今見事に結実してきておられます。最初は医師が中心の研究会だったようですが、今では会員数は2000名を超え、看護師、リハビリテーションスタッフ、薬剤師など多くの職種も参加し、重症心身障害児者の医療看護面から生活面、あるいは教育や心理まで実に幅広い領域から研究、研鑽を報告し合う会に発展し、さらに医療的ケア児や強度行動障害も含め、家庭から地域まで、障害を持った方々を支える研究と実践の場となっています。家庭や地域での医療的ケアのレベルが向上してきた経過にも寄与してこられました。コネクターに関する取り組みのように社会的提言も行っておられます。
皆様ご承知かと思いますが、私ども日本重症心身障害福祉協会は「日本重症心身障害療育学会」を主催しています。似たような名称ですが、当方の会は全国の重症心身障害施設の職員の療育実践活動をベースとし、その経験、提案、そして実践的研究が中心になっています。発表者の最大職種は介護関係(生活支援員、保育士、指導員他)で、看護師、リハビリテーション関係が続きます。施設での療育実践の研鑽を目的とした療育学会と貴学会での研究活動はお互いに補完しあう関係にあると思っています。実際療育学会に携わる専門職の多くは、貴学会の会員でもあります。
現在、日本の制度や仕組みは新しい時代に向けて変化を迫られています。どのような障害を抱え、医療課題を背負っていても、それぞれの人生を充実して送れるように、私たちの貢献が更に求められています。そのためにも改めて貴学会の更なるご発展を祈念いたします。
小林提樹先生の「自分の経験を伝え、発展させていきたい」という願いではじまった貴学会(当初は研究会)は、今見事に結実してきておられます。最初は医師が中心の研究会だったようですが、今では会員数は2000名を超え、看護師、リハビリテーションスタッフ、薬剤師など多くの職種も参加し、重症心身障害児者の医療看護面から生活面、あるいは教育や心理まで実に幅広い領域から研究、研鑽を報告し合う会に発展し、さらに医療的ケア児や強度行動障害も含め、家庭から地域まで、障害を持った方々を支える研究と実践の場となっています。家庭や地域での医療的ケアのレベルが向上してきた経過にも寄与してこられました。コネクターに関する取り組みのように社会的提言も行っておられます。
皆様ご承知かと思いますが、私ども日本重症心身障害福祉協会は「日本重症心身障害療育学会」を主催しています。似たような名称ですが、当方の会は全国の重症心身障害施設の職員の療育実践活動をベースとし、その経験、提案、そして実践的研究が中心になっています。発表者の最大職種は介護関係(生活支援員、保育士、指導員他)で、看護師、リハビリテーション関係が続きます。施設での療育実践の研鑽を目的とした療育学会と貴学会での研究活動はお互いに補完しあう関係にあると思っています。実際療育学会に携わる専門職の多くは、貴学会の会員でもあります。
現在、日本の制度や仕組みは新しい時代に向けて変化を迫られています。どのような障害を抱え、医療課題を背負っていても、それぞれの人生を充実して送れるように、私たちの貢献が更に求められています。そのためにも改めて貴学会の更なるご発展を祈念いたします。
日本重症心身障害学会 創立50周年に寄せて
村尾 晴美
全国医療的ケアライン 代表
このたびは、日本重症心身障害学会創立50周年、誠におめでとうございます。
長年にわたり、重症心身障害のある方々とそのご家族の命と暮らしを支えてこられたご尽力に、心より敬意と感謝を申し上げます。
全国医療的ケアラインは、2021年の医療的ケア児支援法の施行を契機に、都道府県単位の家族会が連携し発足した全国ネットワークです。制度整備が進む一方で、地域間格差や制度の狭間に置かれた子どもたちの課題が改めて顕在化するなか、「地域で会をつくり、他県とつながり、国にも声を届けよう」という思いから設立されました。
重い病気や障害があっても、安心して暮らし続けられる社会の実現を目指し、情報交換や調査、政策提言、啓発活動に取り組むほか、Zoomを活用したオンライン会議や、年に一度開催する全国フォーラムなどを通じて、地域を越えたつながりと学び合いの機会を大切に、制度の谷間にある子どもたちの声を丁寧に拾い、社会に届ける活動を続けています。
そのような私たちにとって、日本重症心身障害学会は、知識の拠り所であり、進むべき道を示す羅針盤です。医療・福祉・教育など多職種が一堂に会し、立場を超えて知恵と経験を分かち合えるかけがえのない学術の場として、重症心身障害をめぐる多様な課題に真摯に向き合う貴学会の姿勢に、私たちは深い共感と学びを得ています。
重症心身障害という言葉に込められた歴史と思想を継承しながら、職種・分野・地域・世代を越えて手を取り合い、ともに希望を拓く実践を重ねていけることを願っております。
今後、医療的ケアが必要な人々の地域での暮らしや人生の選択肢がさらに広がるよう、私たちもまた、当事者や家族の声を丁寧にすくい上げ、貴学会とともに歩んでまいります。
本記念すべき50周年が、重症心身障害のある方々の暮らしと未来をより豊かにする、新たな歩みの第一歩となりますことを、心よりお祈り申し上げます。
長年にわたり、重症心身障害のある方々とそのご家族の命と暮らしを支えてこられたご尽力に、心より敬意と感謝を申し上げます。
全国医療的ケアラインは、2021年の医療的ケア児支援法の施行を契機に、都道府県単位の家族会が連携し発足した全国ネットワークです。制度整備が進む一方で、地域間格差や制度の狭間に置かれた子どもたちの課題が改めて顕在化するなか、「地域で会をつくり、他県とつながり、国にも声を届けよう」という思いから設立されました。
重い病気や障害があっても、安心して暮らし続けられる社会の実現を目指し、情報交換や調査、政策提言、啓発活動に取り組むほか、Zoomを活用したオンライン会議や、年に一度開催する全国フォーラムなどを通じて、地域を越えたつながりと学び合いの機会を大切に、制度の谷間にある子どもたちの声を丁寧に拾い、社会に届ける活動を続けています。
そのような私たちにとって、日本重症心身障害学会は、知識の拠り所であり、進むべき道を示す羅針盤です。医療・福祉・教育など多職種が一堂に会し、立場を超えて知恵と経験を分かち合えるかけがえのない学術の場として、重症心身障害をめぐる多様な課題に真摯に向き合う貴学会の姿勢に、私たちは深い共感と学びを得ています。
重症心身障害という言葉に込められた歴史と思想を継承しながら、職種・分野・地域・世代を越えて手を取り合い、ともに希望を拓く実践を重ねていけることを願っております。
今後、医療的ケアが必要な人々の地域での暮らしや人生の選択肢がさらに広がるよう、私たちもまた、当事者や家族の声を丁寧にすくい上げ、貴学会とともに歩んでまいります。
本記念すべき50周年が、重症心身障害のある方々の暮らしと未来をより豊かにする、新たな歩みの第一歩となりますことを、心よりお祈り申し上げます。
日本重症心身障害学会に期待すること
前田 浩利
日本小児在宅医学会 代表理事
2025年、日本重症心身障害学会が創立50周年を迎えられること、真におめでとうございます。1974年小林提樹先生の「最も弱い子どもたちを守りたい」という熱い想いから貴会が始まったこと、そして、50年という歴史を刻み、多くの成果を産み、日本の医療界に「重症心身障害医療」の確かな流れを興されたこと、心よりの敬意を表したいと思います。私が、代表をさせていただいている日本小児在宅医学会が主なテーマとする「小児在宅医療」も、医療的ケア児者や、在宅緩和ケアを必要とする悪性腫瘍の子どもたち、そして、重症心身障害の子どもや若年成人も対象とします。当会の目指している医療的ケア児者に対するより良い在宅医療や支援の提供は、その多くが、貴会が目指しているものと重なるものだと感じています。その中で、貴会が積み上げてきたものは、当会が学ぶべきものが多く、同じ目的を目指す先達として、目標にするべきと思っています。毎年の学術集会の開催、日本重症心身障害学会誌の定期刊行など、一般的には学会として当然と感じられる方もあろうかとは思いますが、50年継続されるのは大変なご努力と多くの先輩方の情熱があってのことと感じます。今後、当会は、より多くの会員に参加していただき、まだまだ地域格差があると指摘されている「小児在宅医療」をより多くの地域に広げていくことが目標です。その際には、是非、貴会の会員の皆様にご指導をいただき、積極的に連携をさせていただければと願っています。貴会の益々のご発展を祈念して、50周年のお祝いの言葉とさせていただきます。
公募メッセージ(※受付順に掲載しております。)
障害のある人にも学会員にも愛にあふれた学会で
あり続けますように
あり続けますように
徳光 亜矢
医師
私は小児科に入局して5年目に、医局の人事で北海道療育園に配属されました。1997年のことです。すぐに重症心身障害学会に入会し、9月に葉山であった第23回の学術集会で「重症児者における泌尿器科的合併症」として発表したのが、私の重症学会でのデビューです。論文にまとめ、重症学会誌の23号に載せていただきました。この時の学会誌はわら半紙のような紙質のB5サイズで、何とも愛嬌がありました。当時、北海道療育園には医師が少なく、学会もいくつも行けるわけではありませんでしたが、重症学会だけは参加し発表することを自分に課していました。仕事も生活もいろいろ煮詰まっていた時期であっても、学術集会に参加すると先生方の優しさに触れ、モチベーションが高まり、重症心身障害医療の楽しさややりがいを再確認する場でありました。その後、学会誌はA4サイズの立派な紙になり、学術集会の規模もどんどん大きくなり、隔世の感がありますが、今でもこの学会に参加することは私にとってご褒美のようなものです。少しでも重い障害のある人たちの人生を豊かにしようと多職種の人たちが集まるこの会は、他の学術集会とは一線を画しているように思います。これからも障害のある方々の希望になるような重症心身障害学会であり続けますことを祈念しお祝いの言葉と致します。
日本重症心身障害学会と会員の熱意に支えられている私
平野 大輔
作業療法士
この度は、50周年!本当におめでとうございます!私は、作業療法士の養成校卒業後の1年目から重症心身障害児施設で勤務し、同年2004年から貴学会に入会させて頂き、同年開催の第30回学術集会(北海道旭川市)が初めての学術集会への参加でした。
会員とさせて頂いてから、20年以上経過いたしました。貴学会の会員の皆様は、職種や年齢、立場等に関わらず、重症心身障害児(者)に対して、とても熱い方々ばかりで、常に対象児(者)のことを考えております。
このような学会に所属でき、私自身が本当に幸せであり、重症心身障害児(者)に関わり続けていきたいと、繰り返し、何度も思っております!今後の貴学会の益々のご発展をお祈り申し上げます。
会員とさせて頂いてから、20年以上経過いたしました。貴学会の会員の皆様は、職種や年齢、立場等に関わらず、重症心身障害児(者)に対して、とても熱い方々ばかりで、常に対象児(者)のことを考えております。
このような学会に所属でき、私自身が本当に幸せであり、重症心身障害児(者)に関わり続けていきたいと、繰り返し、何度も思っております!今後の貴学会の益々のご発展をお祈り申し上げます。
日本重症心身障害学会50周年記念、おめでとうございます。
船戸 正久
第49回学術集会会長 医師
まず、日本重症心身障害学会50周年記念学術集会の成功おめでとうございます。
私は、2011年に長年働きました急性期病院である淀川キリスト教病院から療育施設である大阪発達総合療育センターへ異動し、初めて療育の世界に足を踏み入れました。そこで発見したのはLifeの新たな意味です。すなわちLifeには「いのち」だけでなく、「生活」、「人生」の意味があるという当然の事実です。そして療育の使命は、「トータルケア(生も死も含む)を多職種協働でどのように大切に支援するのか」ということでした。もう一つ発見したことは、①療育施設のスタッフは非常に優しい、②色々な経験を積んで人間性に富む、③利用者の方々一人一人を大切に思っている、④それぞれの方々の最善の利益をご家族と共に多職種協働で考えられる能力が備わっていることです。これらの文化は、重症心身障害児の父といわれた小林提樹先生始め多くの先達の先生方が残し形成してきた大切な療育の文化です。そうした意味でも療育の世界では、どのような重症児者の方々であってもご本人とご家族を中心に「最善の利益」を多職種協働チームで協力して支援できる基盤をもっていると思われます。この良き伝統が、学術の場である日本重症心身障害学会の土台として今後も引き継がれ、重症児者の方々のより良い「いのちの輝き」のために学問的な研究が多職種でなされる場として益々発展することを祈ります。
私は、2011年に長年働きました急性期病院である淀川キリスト教病院から療育施設である大阪発達総合療育センターへ異動し、初めて療育の世界に足を踏み入れました。そこで発見したのはLifeの新たな意味です。すなわちLifeには「いのち」だけでなく、「生活」、「人生」の意味があるという当然の事実です。そして療育の使命は、「トータルケア(生も死も含む)を多職種協働でどのように大切に支援するのか」ということでした。もう一つ発見したことは、①療育施設のスタッフは非常に優しい、②色々な経験を積んで人間性に富む、③利用者の方々一人一人を大切に思っている、④それぞれの方々の最善の利益をご家族と共に多職種協働で考えられる能力が備わっていることです。これらの文化は、重症心身障害児の父といわれた小林提樹先生始め多くの先達の先生方が残し形成してきた大切な療育の文化です。そうした意味でも療育の世界では、どのような重症児者の方々であってもご本人とご家族を中心に「最善の利益」を多職種協働チームで協力して支援できる基盤をもっていると思われます。この良き伝統が、学術の場である日本重症心身障害学会の土台として今後も引き継がれ、重症児者の方々のより良い「いのちの輝き」のために学問的な研究が多職種でなされる場として益々発展することを祈ります。